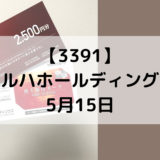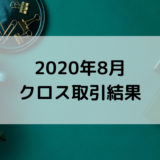こんにちは、あんです。
つみたてnisaを始めて、3年が経ちました。
運用益はこつこつと増えていて、本当に始めてよかったなと思っています。
今回、初心者のためのつみたてnisaの始め方を解説します。
*本記事はアフィリエイトリンクを含みます
つみたてnisaってなに?
投資信託への投資でもらえた分配金や譲渡益(利益)にかかる税金が免除れる制度です。
つみたてnisaの対象商品は、国が認めた投資信託に限定されているので、初心者でも始めやすい仕組みとなっています。
![]() あん
あん
せっかくの制度だから、使わないと損だね。
ちなみに、nisaの正式名称は「少額投資非課税制度」といいますが、そんなことは覚えなくて大丈夫です。
つみたてnisaが向いている人
- 投資初心者
- 投資を少額から始めたい
- 長期でお金を運用しながら貯蓄したい
100円から始められるので、少ない資金から始めたい、投資初心者の方にもおすすめです。
つみたてnisaで購入できるのは、国に認められた投資信託のみなので、その点も初心者にとって安心です。
![]() あん
あん
つみたてnisaのはじめかた
つみたてnisaは、以下の手順で始めます。
①金融機関を決める
②投資先を決める
③運用を開始する
①金融機関の決め方
証券口座を選ぶポイント
- ネット証券を選ぶ
- 信託報酬が安い商品を取り扱っていること
- 積立設定の違い
この3つが、つみたてnisaを運用する証券会社を選ぶポイントになります。
ネット証券がオススメな理由
つみたてnisaは、銀行、証券会社などの金融機関ではじめることができます。
その中で、おすすめは、ネット証券です。
ネット証券がオススメな理由は、
- 投資信託の取り扱い数が多い
- 窓口で、余分な営業をされない
ネット証券は、断然に取り扱い商品の数が多いです。
楽天証券、SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券のようなネット証券では、150以上の商品を取り扱っています。
窓口で余計な営業をされないことも、ネット証券の魅力です。
![]() あん
あん
信託報酬が安い商品とは
信託報酬とは、投資信託の運用などにかかる費用で、運用中 勝手に引かれています。
長期で運用する積立NISAでは、信託報酬は安い方がいいです。
現在、信託報酬が最も安いといわれているのは、eMAXIS SlimシリーズやSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドです。
これらの信託報酬は0.1%前後となっています。
手数料の安さを重視するのであれば、このような投資信託を扱っている証券会社を選ぶといいでしょう。
積立設定の方法で比較
積立設定の方法は、以下の4つのポイントを比較するといいです。
- 最小購入金額
- ボーナス月の増額設定
- 積立金額の増額設定
- クレジット決済の可否
- 買付日
主なネット証券の積立設定について比較してみます。
| 証券会社 | 楽天証券 | SBI証券 |
マネックス証券 | auカブコム証券 |
| 買付手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 最小購入額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 積立金の増額設定 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 |
| ボーナス月増額 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| クレジット決済 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
| ポイント投資 | あり | なし | なし | なし |
| 買付日 | 毎日・毎月 (クレジットは毎月のみ) |
毎日・毎週・毎月 ・隔月・複数日 |
毎日・毎月 | 毎月 |
最小購入額はいずれも100円から投資できますし、ボーナス月に設定額を増額することができます。
大きな違いは、楽天証券ではクレジット決済可能なので、楽天ポイントを貯めることができることです。
クレジット決済の場合は、買付日が、月に1回、日付は1日と決まっています。
楽天ポイントが貯まることが魅力的ですが、買付日が1日ということを気にされて、クレジット決済にされない方もいるようです。
SBI証券と楽天証券
は、積立金の増額設定といって、年の途中でつみたてNISAを始めても、
残りの月でnisa枠を使い切れる金額に設定することができます。
マネックス証券やauカブコム証券などは、月々の設定額は33000円までと決まっていて、
nisa枠を使い切るにはボーナス月の増額するしかないようですね。(制度がときどき変わるので、ご自身でもご確認ください)
②投資先の決め方
- 信託手数料が高すぎない
- 3つの分散投資を行う
信託報酬が高すぎない
上記の章でお話ししたように、信託報酬は高すぎると、運用中常に高い信託報酬が買ってに差し引かれることになるので、
あまりよくないです。
現在、信託報酬が最も安いといわれているのは、eMAXIS SlimシリーズやSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドです。
これらの信託報酬は0.1%前後となっています。
3つの分散投資を行う
リスクを避けるための1つの方法として、分散投資をします。
分散投資とは、①商品の分散・②地域の分散・③時間の分散のことです。
1つ目の商品の分散とは、値動きがことなるものを同時にもつということです。
例えば、株式と債券を比べると、株式が値上がりしているときは、債券は値下がる傾向にあります。
そこで、株式と債券を一緒に持つことで、例えば株式が大暴落したときに、債券でカバーすることができます。
株式と債券の両方をもつといいでしょう。
![]() あん
あん
2つ目の地域の分散とは、例えば日本にばかり投資するのではなく、米国、先進国、新興国などさまざまな地域に分散投資することです。
投資商品の値動きは、その地域の経済の様子や為替の値動きによって、それぞれの動き方をします。
ある保有商品が値下がっても、違う国の商品でカバーできるかもしれません。
![]() あん
あん
その結果、コロナ不況中日本株がなかなか回復せずということがおきました。
地域の分散がしっかりできていなかったんですねー。
今は米国株の比率を増やしたり、コモディティ投資の割合を増やしたりしています。
全世界の株式や債券を運用している投資信託を購入することで、①商品の分散と②地域の分散をすることができます。
3つ目の③時間の分散は、1度にたくさん買うのではなくて、毎日または毎月と時間を分けて買付していくことです。
定期定額で買付を行うことで、高値のときに少しの、安値のときに多くの投資をすることができます。
つみたてNISAでは、定期定額での買付が目的なので、時間の分散ができると思います。
投資信託だけではなく、気になる株式を買付するときも、時間の分散は使えると思います。
株式の売買も、少しずつ買って、少しずつ売るんです。
投資信託は、同じ額を何回にも分けて買うことができます(定額購入法、ドルコスト平均法といいます)が、
株式は、同じ口数を何回にも分けて買う(同量購入法といいます)ことになります。
どちらも、購入額を抑えることができますが、定額購入法の方がコストを安く抑えることができるようです。
まとめ
以上、つみたてnisaの始め方のまとめでした。
わたしは、つみたてnisaを楽天証券で運用していますが、
初心者にも見やすい画面で、商品ラインナップも多く、また楽天ポイントも貯めることができるので、
楽天証券で始めてよかったな、と思っています。
以下に、参考リンクを載せました。投資のことを、勉強することができるサイトです。
参考リンク